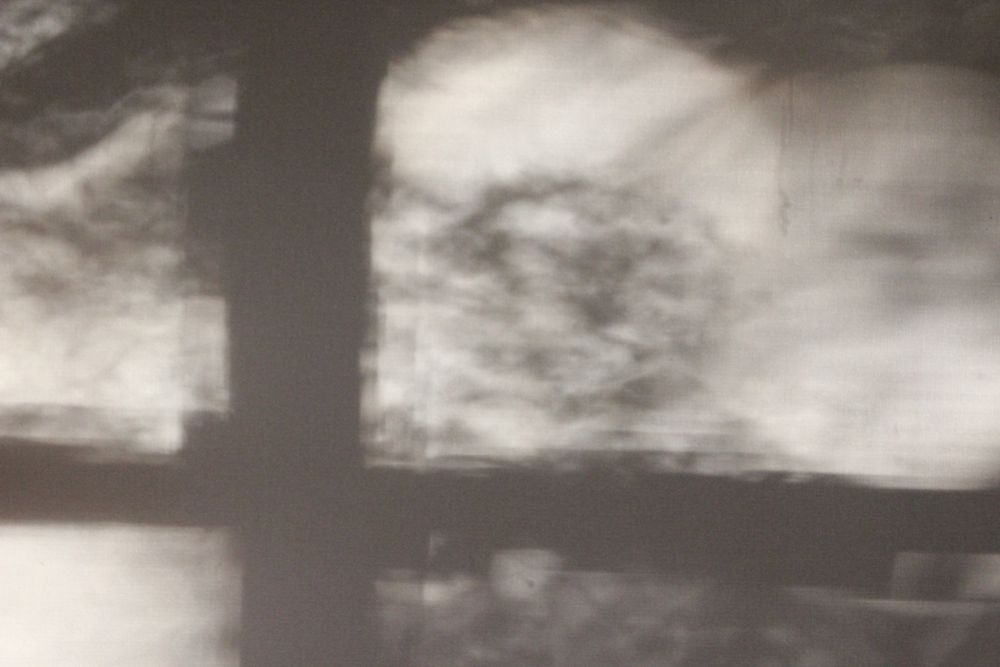映画「福田村事件」が予想外のロングランになり公開劇場数を伸ばしている。この映画の何が面白いのか。きっとそれは誰に聞いてもうまく答えられないのではないか、と思う。なぜなら、森達也という監督が、「うまく答えられないこと」を撮ろうとしているから。言葉というレッテルでは表現しきれないこと。それを撮ろうとしているから。
そもそも森達也監督は監督デビューが「A」という映画だった。オウム真理教がテロを起こし、日本中が大騒ぎになっているその最中、オウム真理教の内側に入り、その日常を撮っていった。その映像に多くの人が驚いた。そして言葉を失った。
「あの凶悪集団が、、、」
「、、、」ではいろんなことが言えるかもしれないが、映画を見るとあの時代の雰囲気ではいいにくいことが見えてきた。そして、それに気づいた人は一人取り残される。
「言いたいが、言ったらどうなるのだろう?」
言い出すことに勇気が必要な何か。日本を覆い尽くしている言語化できない雰囲気に気づかされてしまう。そしてそれに気づくと誰にでも気軽には言えないので一人取り残される。よほど仲が良い、何を言っても許し合える人たちとしか言い合えない「あれ」。
映画「福田村事件」では、関東大震災当時言えなかったであろうことを令和の今、感じさせてもらう。なぜそれが言えなかったのか? 令和の今なら当たり前に言えるようになってきた。でも、と思考が止まる。
令和の今、言えないことがある。
それは注射のことであったり、安倍元首相の暗殺の真相であったり、ウクライナとロシアの背景であったり、海洋放出のことであったり、色々だ。でも、それらは言おうと思えば言える。書ける。恐怖心さえ乗り越えられれば。
「A」でも、「Fake」でも、「i-新聞記者ドキュメント-」でも、森監督は現在に生きている人には見えない、言えない、書けない何かを表現してきた。
映画「福田村事件」の舞台となった当時、そこに生きていた人たちはきっと気づいていなかったであろうセリフが出てくる。もし、映画「福田村事件」をこれから見ようとしている人は、ここから先は読まないほうがいい。そのセリフが出てきた時、僕は泣いてしまった。
関東大震災当時の日本人が言えなかったこと。もしかしたら、思いもしなかったこと。それは「鮮人なら殺してええんか」。
令和の今なら当たり前のことだ。どこの国の人だろうが、殺してはならない。だけど、関東大震災から五日後の、あの映画の舞台となった村では、「鮮人なら殺してええ」となってしまった。それがなぜか、その雰囲気がどうして出来上がっていったのか、それを丁寧に見せられる。
令和の今、積み重なってきた言えないこと。そういうものがあり、いつかにっちもさっちも行かなくなるかもしれないことに目が覚める。群れることで考えなくなるおぞましさ。上の言うことを疑うことなくまにうける恐ろしさ。自分が正しいと思ったら、感情的になる幼さ。
殺戮がおこなわれたあとで、水道橋博士が演じていた在郷軍人会分会長・長谷川の叫び声が耳から離れない。